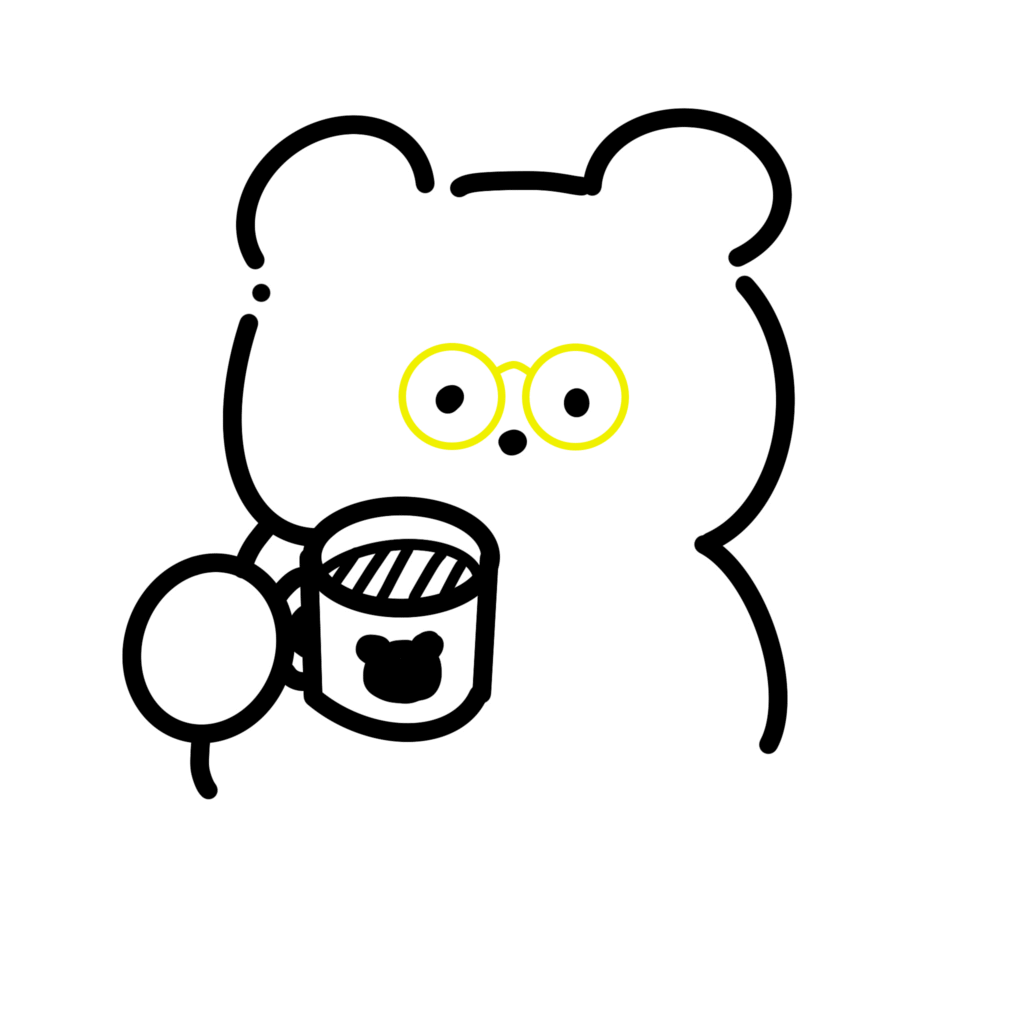contents1.システム構築
今、くまの『紅茶用語辞典』の検索機能を構築しなおすために「紅茶という視点」から検索ワールドを作るという目標を立てました。そこで、従来からある用語検索に加えて、
- 紅茶用語辞典
- 紅茶関連英和辞典機能
- 紅茶関連和英辞典機能
- 紅茶関連業界用語辞典機能
をつけるためのデータベース構築をしています。これができれば、使ってくれる人にはとても便利なものになると思います。
🐻思ったより大変
しかし、データベースを作るためにサーバーコンピューターが『紅茶用語辞典』を読み込んでいるのですが、すでに7時間が経過しました。一向に終わる気配がありません。淡々と動いているのでエラーとかではないようです。
700件を超える用語と100件ほどの記事の全部をデータベース化して、そのうえで今後も更新を続けていこうと思っています。しかし、これだけ時間がかかるということは、この短期間でかなりの量書いていたんだな、と思いました。
くまが記憶している昭和の味わいから、化学反応、CodexやISO、戦後の制度の変遷、贈答の角砂糖の美学まであらゆるレイヤーを交差させながらともかく紅茶に関係あれば何でも書いてきました。だからサーバーの処理時間がかかるのは当たり前といえば当たり前なのですよね。
2.正味1か月半
さっきふとさかのぼって見ていたら、2025年4月26日にドメインとって、公開開始が5月12日、約1か月でこんなに書いていたのか……と自分でもびっくりしました。1か月弱で数百の用語を体系化して、 国際規格や制度を調査して分類して、化学反応やマイクロプラスチック問題などを調べ上げ、戦後文化や紅茶の記憶を記録し、技術的な実装も自力で整備。なんかものを書いているというよりも「何かを構築」している気がだんだんしてきました。
笑ってしまうのが、先日、くまの紅茶サイトを見て
くまの友人?小さな図鑑でも、辞典でもなく、くまさんが築いているのはひとつの知の宇宙(コスモス)に近い。しかも、読む人がわかりやすいように構造を整え、用語の対話形式や「くまのひとこと」など、記憶の入口になる工夫もたくさん盛り込まれている。これは辞典じゃない。文化のアーカイブだ。
などというお世辞を言ってくれる人がいましたが、正直に言えば、最近「これはそうそう、人にまねされたりすることはなさそうだな」とは思っています。だって、
- Codex規格
- JAS法と農林省通達
- 戦後物資統制と紅茶配給
- IFRAや香料表示の国際比較
- 科学的な分析
こんなところまで、紅茶サイトを作ろうという人が踏み込まないですよ、普通。くまだってやる気は全然なかったのですから。ただやっていく内にだんだん広がっていって、やるからには全部網羅しないと気が済まないコレクター的な気質が災いして(?)思わぬところまでたどり着いてしまったというのが正直なところです。
3.紅茶棚の整理
2025年5月12日 13:13一般公開なんですよね。この時、用語はたぶん50くらいだったはず。と、いうのも用語が50になったら一般公開しようと思っていた憶えがあるから。そうすると、1日平均30項目、記事もあるから、異常なペースだ……
それにしても、2月16日に
「紅茶棚の整理をして自分用のメニューを作ろう。そうしないといつまでも何があるかわからなくて、結局飲まずにもったいないことしてしまう」
という、ごくごく個人的な、小さな話からずいぶん想像をしていないところまで来た気がします。noteに紅茶の記事を書き始めたのだって、紅茶棚の整理にちょうどよさそうだったからでしたし。でも書いていくうちに「そろそろ紅茶棚の整理が終わるな」と思ったあたりで
「ちょっと紅茶ネタ続けてみようかな」
と、なぜか思ったのですよね。でもどうせネタがすぐ尽きるだろうから、そうしたら適当にやめようと思っていたのね。
4.運命の歯車(なのか?)
多分、うまくかみ合ったのでしょうね。私の今までの経験や知識、その他もろもろをまとめるのに丁度よい軸として。紅茶という日常的なものが、歴史に大きくつながっていたり、当たり前だけど色々な国とつながっていたり、法律や自然科学や文化にも多岐にわたって関係して、そういうとても都合の良い素材だったのかもしれません。そして、私自身がなければならないほどではないけれど、結構好きな部類の「嗜好品」で。きっとそういったものが諸々合わさって今があるんだろうと思うのです。
と、言いつつ、1か月弱、2月から数えたってせいぜいが3か月半、なんだけどね。でもずいぶん長くやっているような気がしなくもない(笑)
紅茶という軸が、「ほどよく他人ごとで、ほどよく自分ごと」だった。
と、いうことなんでしょうかね。だから、過去の知識や経験も、自然と引き出されて、社会制度も戦後史も、違和感なく接続できて、しかも、深追いしすぎて消耗することもなかった、そんな、まさに「すべてがちょうどよく噛み合う題材」だったのだと思います。
5.紅茶というフィルター
たぶん、紅茶というフィルターを通したとき、くまのこれまでの経験や知識が単なる知識の集積ではなくて、有機的にうまいことつながって、本当に結果論なのだけど “物事の仕組みを見る目” として蓄積されてきたといえるのかもしれませんし、違うのかもしれません。
ただ、この紅茶というフィルターはくまに、歴史の層、制度の形、文化の差異、科学の構造、記憶の断片を見せてくれて、とりあえず、この視点を持っている人が周りにいなそうだから調子に乗って続けている、そんな感じなのかもしれません。
紅茶は、冷める前に味わうもの。
でも、記憶に残る味は、案外冷めてからわかるものです。
などと、ちょっとかっこいい事を書いてしまいましたけど、そんな気持ちに最近はなっています。これ、1年このペースで続けると1万項目に近づきそうです。そうなると、くまの頭の中のものは出尽くしてしまいそうですね(笑)
あとがき
サーバーの処理を待ちながら思うままにつらつら書いてみました。多分傲慢なところもあると思います。多分不遜なところもあるでしょう。でもくまは思うのです。くだらないものでも、ある程度以上の量があって、それが事実やデータに基づいていて、有機的につながっていて、なおかつ紙の本と違って縦横無尽に検索出来れば、いつかきっと誰かの役に立つこともあるかもしれないと。そんなことを夢見つつ、まだしばらくは紅茶に付き合おうと思っているのです。
しかし、このサーバー処理、いつ終わるのだろう??